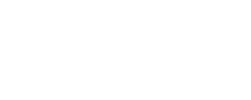鈴与シンワートのサステナビリティ
私たちは、鈴与グループ220年の事業継承を支える「共生(ともいき)」の精神に則り、事業活動を通してさまざまな社会課題に取り組むサステナブル経営を推進することで、新たな価値を創造し、皆様と共に、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
私たちは、鈴与グループ220年の事業継承を支える「共生(ともいき)」の精神に則り、事業活動を通してさまざまな社会課題に取り組むサステナブル経営を推進することで、新たな価値を創造し、皆様と共に、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

データセンターサービス
クラウドサービス
基幹・ビジネスパッケージ
ITインフラ構築・保守運用

S-PAYCIAL with 電子給与明細
S-PAYCIAL with 電子年調申告
S-PAYCIAL with 電子人事申告
POSITIVE
奉行クラウド / 奉行V ERPクラウド
Superstream-NX等、人事・財務会計ソリューション

運転前アルコールチェック&検温クラウドサービス「あさレポ」
従業員エンゲージメント向上支援クラウドサービス 「ここレポ」
Salesforce関連ソリューション

物流業務コンサルティング
物流ITコンサルティング
物流システム開発

データセンターサービス
クラウドサービス
基幹・ビジネスパッケージ
ITインフラ構築・保守運用

S-PAYCIAL with 電子給与明細
S-PAYCIAL with 電子年調申告
S-PAYCIAL with 電子人事申告
奉行クラウド / 奉行V ERPクラウド
Superstream-NX等、人事・財務会計ソリューション

運転前アルコールチェック&検温クラウドサービス「あさレポ」
従業員エンゲージメント向上支援クラウドサービス 「ここレポ」
Salesforce関連ソリューション

物流業務コンサルティング
物流ITコンサルティング
物流システム開発
POSITIVEは株式会社電通総研の製品です。
SuperStream-NXはキヤノンITソリューションズ株式会社の製品です。
奉行クラウド / 奉行 ERPクラウドは株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)の製品です。
Salesforce、Sales Cloud、及びその他はSalesforce,Inc.の商標です。

Copyright © 2018-
SUZUYO SHINWART Corp. All rights Reserved
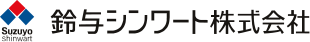
プライバシー情報
お客様が当サイトを訪れると、ブラウザに情報が保存される、またはブラウザに保存された情報が取得されることがあります。情報の主な保存先は Cookie であり、対象となるのはサイト訪問者に関する情報、サイト訪問者による設定、デバイス情報などです。これらの情報はサイトを正常に機能させる目的を中心に使われます。個人を直接特定できる情報が保存されることは通常ありませんが、Web サイトのパーソナライズに使われることはあります。鈴与シンワートではプライバシーの権利を尊重しており、一部の Cookie については有効化を拒否できるよう配慮しています。各カテゴリをクリックすることで、それらの Cookie に関する詳細を確認し、当サイトにおけるデフォルト設定を変更できます。ただし、一部の Cookie を無効化した場合、サイトの利用やサービスの利用に影響が出る可能性があります。詳細情報
不可欠な Cookie
このカテゴリの Cookie は、Web サイトが正常に機能する上で欠かせないものであり、無効にできません。プライバシー設定、ログインやフォームでの入力など、サイトの利用に必要な情報に限り保存されます。ブラウザの設定により、不可欠な Cookie を警告またはブロックできますが、ブロックすると当サイトの一部は機能しなくなります。不可欠な Cookie に個人情報は保存されません。
パフォーマンス Cookie
このカテゴリの Cookie は、訪問回数とトラフィックソースの種類を数えるために使われます。これらの情報は、当サイトのパフォーマンスを測り改善する目的で利用されます。たとえば最も訪問者が多いページと少ないページや、訪問者が開いたページなどを追跡します。情報はすべて集約されるため、匿名性が維持されます。パフォーマンス Cookie を無効にすると、最後に訪れた日時を把握できないため、当サイトのパフォーマンスが判断できなくなります。
ターゲティング Cookie
このカテゴリの Cookie は、広告パートナーにより当サイト経由で設定される場合があります。訪問者の興味関心について記録し、それらと関連性の高い広告をサイト上で表示させる目的で使われます。個人情報が直接保存されることはありませんが、お使いのブラウザとデバイスに関する固有の情報が利用されます。ターゲティング Cookie を無効にすると、広告のターゲティング度合いが低下します。